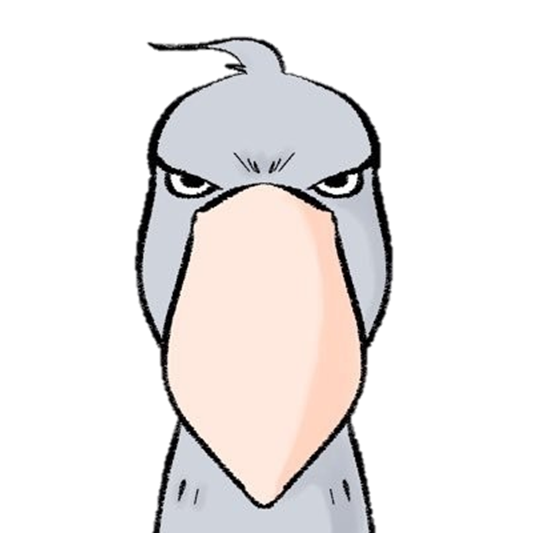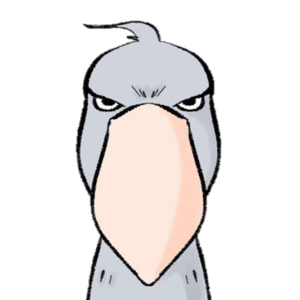9月4日は「クラシックの日」──古くさい?オワコン?……いやいや!待って!!
「クラシック」という言葉を耳にしたとき、あなたはどんなイメージを思い浮かべるだろうか。
モーツァルトの軽やかな旋律? それともベートーヴェンの力強い交響曲? あるいは、格式高いコンサートホールの雰囲気?
9月4日は「クラシックの日」。これは日本クラシック音楽事業協会が1990年に制定した記念日で、語呂合わせの「9(ク)4(ラシック)」から生まれた。普段は少し堅苦しいと思われがちなクラシック音楽を、もっと気軽に楽しんでもらおうという願いが込められている。
だが、そもそも「クラシック」とは何だろう。なぜクラシック音楽と呼ばれるのか。その歴史をひもとくと、思いのほか奥深い世界が見えてくる。
クラシック=古典?
「クラシック(classic)」は英語で「古典的な」「模範的な」という意味を持つ。もともとは古代ギリシャやローマの文学・芸術を指して使われていた言葉だ。そこから転じて「時代を超えて価値が認められる芸術」を広く意味するようになり、特に音楽の分野では18世紀後半から19世紀初頭にかけて活躍した作曲家たちの音楽を中心に「クラシック音楽」と呼ぶようになった。
つまり「クラシック音楽」とは、ある特定の様式や形式に基づいた音楽でありながら、同時に「長く愛され続けてきた芸術作品」というニュアンスを含んでいる。
歴史をざっくりたどる
クラシック音楽の歴史は、ざっくり区分すると次のようになる。
- バロック時代(1600〜1750年頃)
・バッハ、ヘンデルらが活躍。
・装飾的で壮麗な音楽。オペラやカンタータも登場。 - 古典派(1750〜1820年頃)
・モーツァルト、ハイドン、ベートーヴェン初期。
・シンプルで均整のとれた旋律、ソナタ形式が確立。 - ロマン派(1820〜1900年頃)
・ショパン、シューベルト、ワーグナー、ブラームス。
・個人の感情表現が重視され、劇的で華やかな作品が多い。 - 近現代(20世紀以降)
・ドビュッシー、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチ。
・調性を崩したり、民族音楽を取り入れたり、多彩な実験が行われる。
こうして見てみると、「クラシック」という言葉は実際には時代ごとの変化を含んでおり、一枚岩ではない。むしろ進化と実験を繰り返してきた歴史そのものがクラシック音楽なのだ。
知ると楽しいクラシック・トリビア
クラシック音楽には、ちょっとした雑学が山のようにある。いくつか紹介しよう。
🎼 ベートーヴェンの耳の秘密
「楽聖」と呼ばれるベートーヴェンは、後半生でほとんど耳が聞こえなかった。にもかかわらず「第九」などの大作を生み出した。彼は頭の中で音を鳴らす“内的聴覚”を駆使して作曲していたという。
🎼 モーツァルトは速筆?
モーツァルトの楽譜を見ると、ほとんど修正跡がない。まるで最初から完成形が頭の中にあったかのように書き上げている。天才の象徴のようなエピソードだ。
🎼 「ブラボー!」の掛け声はイタリア語
クラシックコンサートのアンコールで「ブラボー!」と叫ぶのはイタリアの伝統に由来する。男性歌手には「ブラーヴォ」、女性なら「ブラーヴァ」と性別で言い分けるのが本来のルールだ。
🎼 指揮者は必須?
実は小編成のオーケストラなら指揮者がいなくても演奏可能。ベートーヴェンやモーツァルトの時代には、ピアノ奏者がリーダーを務めながら演奏することもあった。
日本とクラシック
日本でクラシック音楽が本格的に根付いたのは明治時代。文明開化の流れの中で、西洋文化の一環として輸入された。やがて音楽教育に組み込まれ、吹奏楽や合唱を通じて全国に広まった。
戦後はNHK交響楽団の存在や、世界的な指揮者・小澤征爾の活躍などによって、クラシックは一般にも広く知られるようになった。最近ではゲームやアニメ、CMにもクラシックが使われるため、気づかないうちに耳にしている人も多いだろう。
「クラシック=敷居が高い」は誤解かも
クラシック音楽というと、「長い」「難しい」「眠くなる」と思う人もいるかもしれない。だが、実はクラシックは驚くほどポップな存在でもある。
例えば、運動会でおなじみの「天国と地獄」の序曲(オッフェンバック)、フィギュアスケートで流れるチャイコフスキーの「白鳥の湖」、テレビ番組のジングルに使われるバッハの「G線上のアリア」……。すでに私たちの生活の中でクラシックは自然に溶け込んでいるのだ。
クラシックの未来
デジタル配信やYouTubeの普及によって、クラシック音楽はかつてないほど身近になっている。検索ひとつで、世界の名演を無料で楽しめる時代だ。さらにAI技術が進むことで、失われた演奏様式を再現したり、未完成の作品を“完成”させる試みも始まっている。
クラシックは決して「過去の遺産」ではない。今もなお、新しい形で生き続けている音楽文化なのだ。
まとめ
9月4日の「クラシックの日」は、単に語呂合わせで決められた記念日ではない。
クラシックが私たちの日常に根づき、時代を超えて愛され続けていることを思い出す日だ。
クラシック音楽は難解でも堅苦しくもない。むしろ人間の感情を最も深く、時にユーモラスに表現した“普遍の芸術”。
この日をきっかけに、ちょっと気軽にクラシックを聴いてみるのも良いかもしれない。
もしかすると、あなたの心にぴったり寄り添う「運命の一曲」に出会えるかもしれない。
――――――