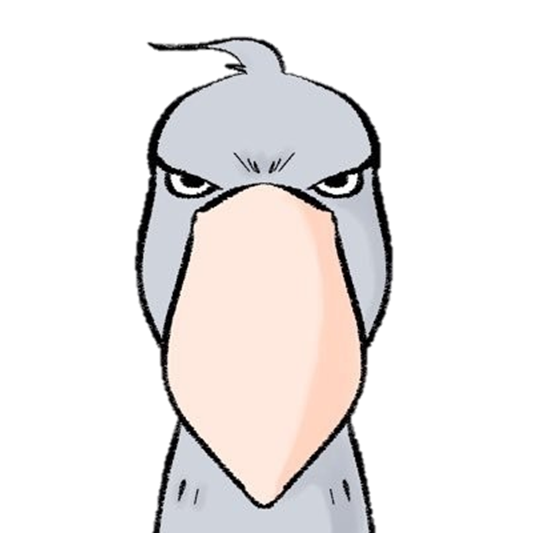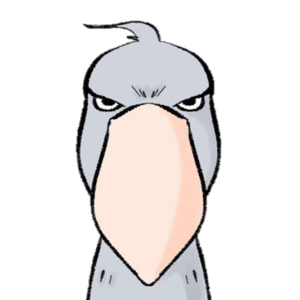8月28日はオールドメディア??とんでもない!!革新メディアでした!
みなさんは「8月28日」が何の日かご存じでしょうか?
実は1953年(昭和28年)のこの日、日本で初めて民間放送によるテレビ番組がスタートしました。現在では当たり前のように見ている民放テレビですが、その始まりは戦後復興の真っただ中、まだテレビ自体がぜいたく品だった時代のことだったのです。
この「民放テレビスタートの日」は、日本のメディア史において大きな節目。今回は、その歴史的背景や当時の番組事情、そして現代に至るまでの民放テレビの変化について、紐解いてみます。
◆ 日本初の民放テレビ放送が始まった日
1953年8月28日、日本テレビ放送網(現在の日本テレビ)が日本初の民間放送局としてテレビ放送を開始しました。
実はその少し前、同じ年の2月にはNHKがすでにテレビ放送を開始しており、「日本初のテレビ放送」はNHKに軍配が上がります。ただ、NHKはあくまで公共放送。一方で日本テレビは「民間放送」として広告収入を軸に運営されるため、視聴者に楽しんでもらえる娯楽性やスポンサーとの結びつきが強いのが特徴でした。
つまり、8月28日は「テレビが国民のものへと一気に近づいた日」と言えるのです。
◆ 初めての民放番組と放送内容
初回放送は白黒テレビによる生中継。
記念すべき番組は「プロレス中継」でした。当時の人気レスラー、力道山の試合が中継され、街頭テレビの前には黒山の人だかりができたといいます。
この「街頭テレビ」という言葉、今の若い世代にはあまりなじみがないかもしれません。当時、家庭用テレビはまだ高価で普及しておらず、駅前や商店街に設置された大型テレビの前に人々が集まり、まるでお祭りのような熱気の中で観戦していました。特に力道山の空手チョップが炸裂するシーンになると、見知らぬ人同士でも一緒に大歓声を上げたそうです。まさにテレビが「国民的な体験」を作り出した瞬間でした。
◆ 高嶺の花だったテレビ
ちなみに1953年当時、テレビ受像機の価格は1台約30万円。
今の物価に換算すると数百万円に相当するといわれています。庶民にはとても手が届かず、せいぜい街頭テレビや親戚・知人の家で見せてもらうのが精一杯でした。
それでも翌年の1954年にはカラー放送の試験放送が行われ、1960年代後半には白黒テレビからカラーテレビへの普及が一気に進んでいきます。さらに1970年の大阪万博がその流れを加速させました。こうした流れを考えると、民放テレビの登場が日本人の暮らしにどれほどインパクトを与えたか、よくわかります。
◆ 民放がもたらした娯楽の多様化
NHKがニュースや教育的な番組に力を入れていたのに対し、民放は「スポンサーがつくこと=人気を取らなければいけない」という宿命がありました。そのため、ドラマ、バラエティ、音楽番組、スポーツ中継など、娯楽性の高い番組が次々と誕生しました。
昭和30年代には「光子の窓」や「シャボン玉ホリデー」などのバラエティ番組が人気を博し、昭和40年代には「巨人の星」「仮面ライダー」などのドラマ・特撮シリーズが子どもたちを夢中にさせました。さらに音楽番組では『ザ・ベストテン』『夜のヒットスタジオ』といった大型番組が国民的な注目を集めました。
こうして、民放テレビは単なる娯楽を超えて「時代の空気をつかむ装置」としての役割を果たしてきたのです。
◆ 現代の民放テレビとその存在意義
さて、2025年の今を見てみると、テレビの存在感は以前よりも揺らいでいます。YouTubeやNetflix、SNSなど、個人が自由に情報を選び取れる時代になり、「テレビ離れ」という言葉もよく聞かれるようになりました。
しかし、災害時や大きな事件のとき、やはりテレビは信頼できる情報源として強さを発揮します。また、紅白歌合戦やスポーツの国際大会など「みんなで同じものを同じ瞬間に共有する体験」は、テレビならではの魅力だといえるでしょう。
さらに近年では、地上波だけでなくBS・CS放送やインターネット同時配信など、テレビとネットの境界もあいまいになってきました。これもまた、民放テレビが時代の変化に適応してきた証拠だといえます。
◆ まとめ──テレビのこれからを考える日
8月28日の「民放テレビスタートの日」は、単に「テレビが始まった記念日」ではなく、日本人の生活スタイルや価値観を大きく変えた出来事を思い出す日でもあります。
街頭テレビに群がり、力道山の試合に熱狂した人々。
家族みんなでちゃぶ台を囲み、茶の間でドラマやバラエティを楽しんだ時代。
そして今、スマホで番組を見ながらSNSで感想を共有する現代。
そのどれもが、民放テレビがあったからこそ生まれた風景です。
テレビは形を変えながら、これからも人と人をつなぐメディアであり続けるでしょう。
今日8月28日、ふとテレビをつけながら「そういえば、民放ってこんな歴史から始まったんだな」と思い出してみるのも面白いかもしれません。