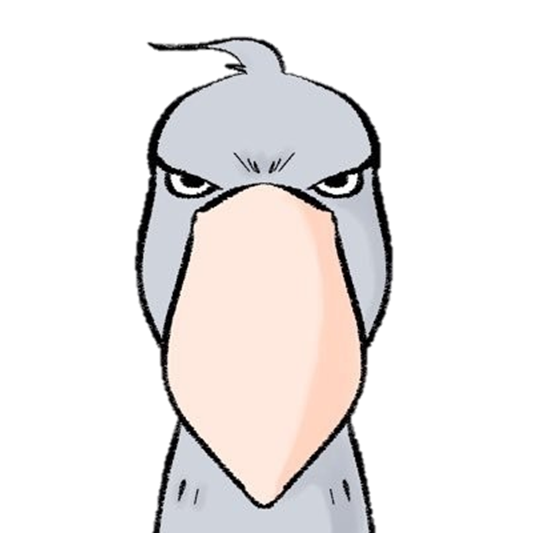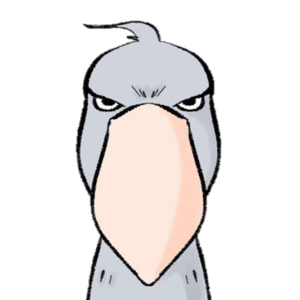ドラえもんの誕生日に寄せて―随所に光る藤子不二雄先生の遊び心
9月3日。この日を聞いてピンと来る人は、相当なドラえもんファンかもしれない。そう、未来の国からやって来た猫型ロボット「ドラえもん」の誕生日である。もっと正確にいえば、22世紀の2112年9月3日に松芝(まつしば)ロボット工場で誕生した、という設定になっている。2112年といえば、まだ人類にとっては遠い未来。けれども物語の中でドラえもんはすでに生まれていて、21世紀を生きるのび太のもとにやってきているのだ。この少し不思議な時系列感こそ、ドラえもんの魅力を形づくっている。
今回は「誕生日記念コラム」として、誰かに思わず話したくなるような“ドラえもんトリビア”をたっぷり紹介していこう。子ども時代に親しんだ人も、大人になってから読み返している人も、きっと「へぇ〜!」と唸るはずだ。
なぜ「9月3日」なのか?
ドラえもんの誕生日が9月3日と設定されているのは偶然ではない。名前の由来と密接な関係がある。
「ドラ」は「ドラ猫」から、「えもん」は古風な語尾「〜えもん」から来ている。さらに数字に置き換えると、「ドラ(ド=0、ラ=6?)」「えもん(3)」など諸説あるが、公式的には「9(ド)・3(ラ)」の語呂合わせ説が有力とされる。のちにアニメや関連書籍でも「ど(9)ら(3)」という遊び心ある語呂合わせが説明され、ファンの間で広く知られるようになった。
ちなみに未来の2112年という年号は、原作者の藤子・F・不二雄が生きた20世紀からちょうど100年後をイメージして設定されたともいわれている。つまり、「100年後の未来にも愛される存在にしたい」という願いが込められているのだろう。
実は“耳があった”ドラえもん
今でこそ、青くて丸い顔に三本ひげがチャームポイントのドラえもんだが、初期設定では「耳」がついていた。製造された時には、ちゃんとネコ型ロボットらしい耳があったのだ。しかしネズミ型ロボットにかじられて失ってしまい、ショックで青ざめた結果、現在のカラーになったという有名なエピソードがある。
この「青ざめた」という設定は秀逸だ。普通なら「塗装が落ちた」とか「設計不良」などの説明がされそうだが、ドラえもんは“心を持つロボット”として描かれている。だからこそ、悲しみやショックを体の色に反映させたのだろう。子ども向けでありながら、心理描写として非常に奥深い。
重さは129.3kg?その理由
公式設定によれば、ドラえもんの身長は129.3センチ、体重は129.3キロ、胸囲も129.3センチ。すべてが「129.3」で統一されている。これは単なる覚えやすさのためではなく、「誕生日=9月3日」にちなんでいる。1(い)、2(ぶ)、9(く)、3(さ)と読めば「のび太(伸びっくさ?)」や「ドラ(どらくさ?)」につながるとする説もあるが、実際には藤子プロの遊び心が込められている。こうした数字の統一感は、子どもにも親しみやすく、なおかつ話のネタになる。
ちなみに体重129.3キロというのはなかなかの重量感。作中でしばしばのび太が抱きついて転んだりするが、あれは現実に換算すると相当危険なはず。だがそこは“マンガ的お約束”として受け入れられているのも面白いところだ。
ポケットの中の宇宙
ドラえもんといえば四次元ポケット。中からは未来の便利道具が次々と取り出される。だがあのポケット自体にもユニークなトリビアがある。
まず「四次元」とは、単に“どこまでも広がる空間”というだけでなく、時間的な概念も含んでいる。つまりポケットの内部は空間だけでなく時空そのものに接続されている可能性がある。藤子・F・不二雄はSF作家としても一流であり、そうした理論的な遊びを子ども向けマンガに巧みに織り込んでいたのだ。
さらに面白いのは、ドラえもんはしばしば道具を取り出すのに“探し回る”ということ。もし完全に整理されていれば、一瞬で取り出せるはずだが、わざとごちゃごちゃした描写を入れることで「親しみやすさ」と「おっちょこちょいなキャラ性」を際立たせている。ここに藤子・F・不二雄のユーモアが光っている。
海外でも大人気――国ごとに異なる“解釈”
日本の国民的キャラクターであるドラえもんは、すでに海外にも広く輸出されている。中国、インドネシア、タイなどアジア諸国を中心に放送されており、とりわけ中国では「機器猫(ジーチーマオ)」の名前で知られている。
面白いのは、国ごとに“解釈”が微妙に異なる点だ。例えばアメリカでは長らく放送されなかったが、2014年にディズニーXDで英語版が放送される際、のび太の名前は「Noby」、しずかちゃんは「Sue」といった具合にローカライズされた。さらにお風呂シーンなどは放送倫理の違いからカットされるなど、文化的な修正も施されている。これもまた、世界的に愛される作品だからこその面白い現象といえるだろう。
ドラえもんは“ロボットか、友だちか”
ドラえもんはロボットである。しかし物語を通じて描かれているのは、“友情”や“家族愛”といった極めて人間的なテーマだ。のび太を助けるために未来から来たはずが、気づけばただの守護者ではなく、同じ時間を共有する“親友”のような存在になっている。この二重性が作品の奥深さを生んでいる。
藤子・F・不二雄は、未来の科学技術を単なる道具として描くのではなく、それを通して「人間の弱さ」「成長」「絆」を描いた。だからこそドラえもんは世代を超えて愛される。誕生日という設定ひとつにも、そうした物語の哲学がにじみ出ているのだ。
まとめ――“未来に残る青い夢”
9月3日は、未来に向けての「希望の日」でもある。2112年に生まれたドラえもんは、私たちの世界ではまだ誕生していない。けれども彼の存在は、すでにマンガやアニメを通じて現実の文化に深く根付いている。これはある意味で、「フィクションが現実を先取りしている」象徴だろう。
ひみつ道具は実際には存在しない。しかし、タケコプターやどこでもドアに憧れて技術者になった人は少なくない。AIやロボット技術の進歩が語られるたびに、ドラえもんの名前が引き合いに出されること自体が、その影響力の証明である。
だからこそ、9月3日は単なるキャラクターの誕生日ではなく、“未来に夢を見る日”として楽しむべきだ。ドラえもんがのび太に寄り添ったように、私たちも未来の世代に夢を手渡していく存在になりたい。
青いロボットが生まれるその日まで――私たちは「ドラえもんの誕生日」を祝い続けていくに違いない。