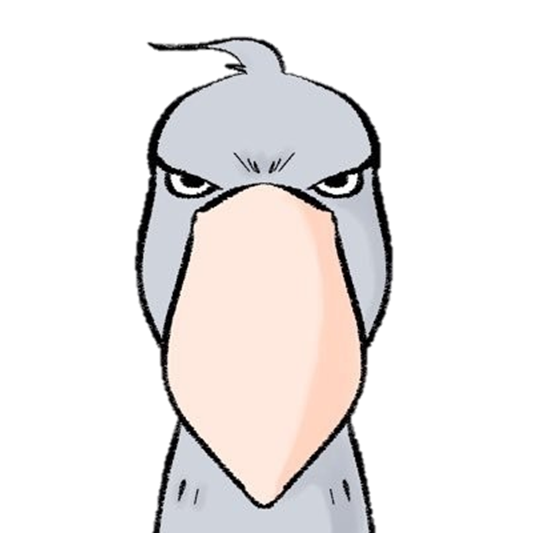バッハ・ベートーヴェン・ブラームス ― 「3B」というブランドの裏側
皆さん、こんぬつは!!高校受験まではとてもクラッシック曲に興味津々だったけだま。です(‘ω’)残念ながら高校に入った瞬間からまるっきり聞かなくなりましたが……
そんな私が語るのはおこがましい話かもしれませんが、現代社会においても通用するブラームスという天才の自己プロモーション力には学ぶことは多いかもしれません。
私のようにクラシック音楽に詳しくなくても、「バッハ」「ベートーヴェン」という名前を耳にしたことのない人はいないでしょう。そして、音楽の世界では、この二人に「ブラームス」を加えた「3B」という呼び方が存在します。ドイツ音楽の伝統を象徴する“三大巨匠”という位置づけで、音楽史の教科書にもたびたび登場します。しかし、この「3B」という呼び名は、単なる歴史的必然ではなく、実は19世紀のある作曲家の戦略によって生まれ、定着したものでした。今回は、3人それぞれの業績を紹介しつつ、「3B」を仕立て上げたブラームスのプロモーション力に光を当ててみましょう。
1. なぜ「3B」なのか?
「3B」という言葉が定着したのは19世紀後半。バッハ(Bach)、ベートーヴェン(Beethoven)、ブラームス(Brahms)という3人の名前の頭文字がすべて“B”であることも、キャッチーな響きを生みました。しかし、同じ時代を彩った偉大な作曲家は他にも数多くいます。交響曲の父と呼ばれるハイドン、歌曲王シューベルト、さらには歌劇界の巨人ワーグナー。なぜ彼らではなく、3Bが選ばれたのか?ここに、当時の音楽界の潮流と、一人の作曲家の意図が関わってきます。
2. バッハ ― “音楽の父”としての再発見
ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685-1750)は、現在でこそ「音楽の父」と称される存在ですが、生前は決してヨーロッパ全土で名声を轟かせたわけではありません。彼は主に教会や宮廷の職に就き、宗教音楽や鍵盤曲、対位法を駆使した緻密な作品を数多く残しました。しかし、彼の死後、その音楽は急速に忘れ去られていきます。理由は、当時の流行が「明るく洗練された古典派の音楽」(ハイドンやモーツァルトの時代)に移っていったからです。
バッハ再評価の転機は1829年、作曲家フェリックス・メンデルスゾーンが「マタイ受難曲」をベルリンで復活演奏したことに始まります。この演奏はセンセーショナルな反響を呼び、バッハの名声は“忘れられた巨匠”から“永遠の古典”へと変貌しました。以降、バッハは対位法と和声の究極の達人として音楽教育の根幹に据えられ、19世紀の作曲家たちの理想像となります。
3. ベートーヴェン ― “楽聖”の誕生
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)は、バッハと異なり生前から広く知られた存在でしたが、その評価が“楽聖”とまで高まったのは死後のことです。ベートーヴェンはハイドンやモーツァルトが築いた古典派の形式を土台に、劇的な表現力を作品に吹き込みました。交響曲第3番「英雄」はナポレオンへの敬意と失望を映し、交響曲第9番「合唱付き」は「人類愛」の象徴として世界中で演奏されるようになりました。
彼の音楽は、19世紀のロマン主義思想、市民社会の台頭と結びつき、「芸術家が権力者に仕えるのではなく、自由な創造者である」という新しい理想像を体現しました。そのため、ベートーヴェンは単なる作曲家ではなく“時代の象徴”となり、肖像画や銅像、音楽祭などを通じて神格化されていきます。
4. ブラームス ― 「3B」を仕立てた男
ヨハネス・ブラームス(1833-1897)は、19世紀後半のウィーンで活躍した作曲家です。彼は当時の音楽界において「進歩派」と「保守派」の激しい対立の中にいました。進歩派の代表はワーグナーとリスト。革新的な和声、無限旋律、標題音楽を提唱し、オペラや交響詩で新しい音楽の未来を切り開こうとしていました。
一方、ブラームスは「絶対音楽」、つまり言葉や物語に依存しない純粋な音楽の価値を重視し、伝統的な形式を守る立場を取りました。しかし、単に「古いものを守る人」と見られては埋没してしまいます。そこで彼は、自分を「バッハ、ベートーヴェンの正統な後継者」と位置づける戦略を取ります。評論家エドゥアルト・ハンスリックとの連携により、バッハの対位法、ベートーヴェンの構築力を継承した“3人目のB”というイメージが広められていきました。
ブラームスの作品は確かに高い完成度を誇りますが、同時にその評価を「ブランド戦略」で強固にしたのです。
5. 「3B」の影響力と問題点
「3B」はドイツ音楽の伝統を象徴する看板となり、音楽史教育でも中心に据えられました。しかし、その裏には「誰が伝統を代表するか」という選別があります。ハイドンやシューベルト、さらには同時代のワーグナーやリストが外されたのは、ブラームスが推した「絶対音楽の系譜」という枠組みに合わなかったためでした。
もちろん、3Bの3人が歴史的巨匠であることに疑いはありません。ただし、この呼び名が普及した背景には、芸術が政治や思想と密接に関わっていた19世紀特有の事情、そして一人の作曲家のイメージ戦略があったことは忘れてはなりません。
6. 結論 ― ブラームスのプロモーション力を称えて
こうして見てくると、「3B」という言葉は、ブラームスの音楽と同じくらい彼の戦略眼を物語っています。自分の立場を明確にし、過去の巨匠をうまく“味方”につけることで、自身の音楽を正統の中心に据えたのです。これは現代のマーケティングにも通じる先見性と言えるでしょう。
今日、世界中で「3B」が語られるたび、そこには単なる偶然ではない、歴史を作った人々の意思と努力が刻まれています。そして、その中核にブラームスの見事なプロモーション力があったことを忘れないとき、私たちは音楽の歴史をより立体的に理解できるのです。