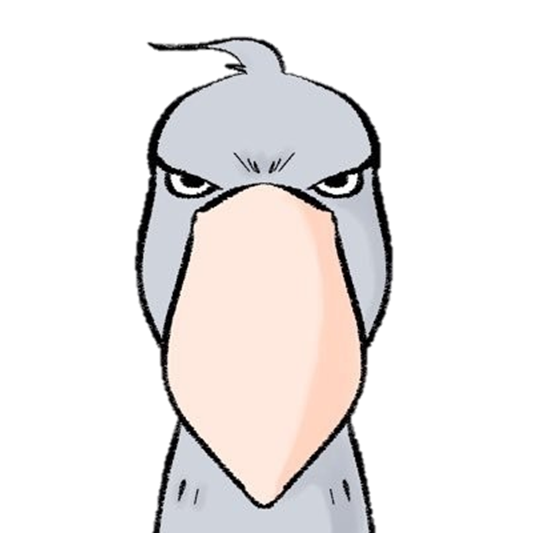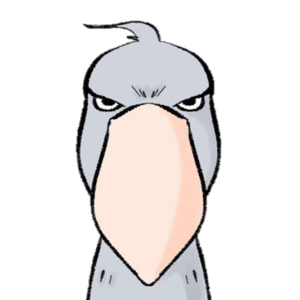街角の保冷バッグ販売を追う:新しい働き方か、それとも闇のビジネスか
皆さん、こんぬつは!!若い娘さんには目がない、けだま。です(‘ω’)ノ
でも、「目がない」って変な表現だと思いませんか?目がないなんて興味の無い言い回しのくせに実は人一倍興味津々なのだから、正確には「若い娘さんには目がある」もしくは「若い娘さんは目に入れても痛くない」くらいがより正確だと思いませんか?
……そもそも私なぞが若い娘さんとどうにかなるって、目がないことは間違いありませんが……
(; ・`д・´)苦笑
とまあ、前置きはここまでにして、私の先日の話……
先日、街を歩いていたらキャリーバッグに謎ののぼりを立てて若い娘さんが1000円くらいのお菓子を売って歩いていた訳ですよ。実に危ないところでしたが、ギリギリ購入を回避できた私ですが、ふと、皆さんも遭遇したことがあるであろう彼ら彼女らが、一体いずこより来りて、いずこへ去るのか深掘りしてしてみようと思います!!(/・ω・)/
✨光:一見すると華やかに見えるポジティブな顔
🌟1. ノマド感覚?自由な働き方スタイル
保冷バッグ販売の最大の特徴は「自由度」です。店舗を持たず、商品とバッグさえあればどこでも仕事ができる。シフトに縛られず、自分のペースで街を歩きながら販売する姿は、まさに“ノマド的”な働き方にも見えます。固定のオフィスを持たずにPCひとつで仕事をする人が増えたのと同じように、物販でも「場所に縛られない自由さ」を体現しているわけです。例えば、ある20代の男性販売員は「昨日は渋谷、今日は上野。気分によって場所を変えられるのがいい」と語っています。確かに、会社に出勤せず、自分の判断で動けるのは魅力的に映ります。
💡2. 固定費ゼロの画期的営業モデル
通常、商売には「家賃」「光熱費」「内装」などの固定費がかかります。しかし、この販売はほぼゼロ。バッグと台車、商品があればすぐに始められ、必要なのは自分の体力と笑顔くらい。初期投資も少なく、スモールスタートが可能な点では、画期的な営業手法といえるでしょう。ある販売員は「最初はアルバイト感覚で始めたけど、思ったより身軽で、出費がほとんどないのがいい」と話していました。販売場所を移動できるため、人通りの多いエリアやイベント帰りの人波を狙うなど、柔軟な戦略も取れます。
🌱3. フードロス削減への貢献
さらに見逃せないのが「食品ロス削減」への貢献です。賞味期限が近い商品や規格外品を活用することで、本来なら廃棄されてしまうお菓子が消費者の手に渡ります。近年問題になっているフードロスの削減という点では、社会的にも意味のある取り組みに見えます。ある主婦の方は「安く買えるだけじゃなくて、廃棄が減るなら良いことをした気持ちになる」と話しており、消費者の満足感にもつながっているようです。
⚠️闇:笑顔の裏に潜む“甘くない現実”
ところが、この保冷バッグ販売には裏側があります。表向きは「自由でスマートな働き方」や「フードロス削減」という顔をしていても、実際の構造をのぞくとかなり複雑で、決して手放しで褒められる仕組みではありません。
🛒1. 商品はどこから来るのか?
保冷バッグに詰められたお菓子の多くは、以下のようなルートから流れてきます。
- 規格外品・余剰品:形が崩れていたり包装不良で流通に乗せられないもの。
- 卸問屋の在庫処分:売れ残りや賞味期限間近の商品。
- 倒産品や輸入菓子の処分:小売業者や輸入会社が潰れた時に残った在庫。
例えば、ある販売員は「メーカー名は聞いていない。とにかく“訳あり品”として渡されるだけ」と証言しています。つまり、大手メーカーが直接この販売スタイルを運営しているわけではなく、多くは“二次流通”や“訳あり品”です。中には「どこから来たのかよく分からない」怪しい商品が混ざることもあります。
💰2. 元締めが笑うビジネスモデル
元締め(業者)は大量の商品を倉庫で抱え、販売員に渡します。その仕組みはこうです:
- 商品の仕入れ値は定価の1〜2割程度。500円のクッキーなら50〜100円で仕入れる。
- 販売員に「1袋1000円で売れ」と指示。
- 実際の原価は200円程度でも、定価のように売らせる。
- 販売員が売った1000円のうち、取り分は300〜400円程度。残りは元締めの懐へ。
販売員は汗水流して歩き回っても、実際に手元に残るのは少額。元締めは販売員を多数抱え、リスクも労力も背負わずに利益を得る構図になっています。ある元販売員は「結局、自分たちは駒でしかなかった」と振り返っています。
🥵3. ノルマと自己負担の現実
販売員はアルバイトではなく「業務委託」という扱いにされることが多く、社会保険や労働保険はなし。売れ残れば自腹で買い取らされるケースもあり、ノルマを課されることさえあります。ある女性販売員は「3袋だけ売れ残ったら、それを給料から差し引かれた。実質赤字の日もあった」と語っています。自由に働けるどころか、実際には歩合制とノルマに苦しむ例も珍しくありません。
🚫4. 法律的グレーゾーン
本来、路上での販売には道路使用許可や保健所への届け出が必要です。しかし実際には、無許可で販売しているケースが大半。食品衛生法上の「移動販売業」のルールを守っていない可能性もあり、消費者にとっては安全性の保証がないのが現実です。ある市民からは「販売員が歩きながら商品を触っていた。衛生的に大丈夫なのか心配」という声も上がっています。
🤔5. 消費者に潜むリスク
「賞味期限が近いから安い」という説明は一理ありますが、中には表示がはがされていたり消されている商品も見られます。そうなると本当に安全なのか判断できません。さらに、スーパーの値引き品よりも割高に感じるケースすらあり、“お得”という言葉に惑わされやすいのです。ある購入者は「安いと思って買ったら、スーパーの半額セールの方がずっと安かった」と苦笑いしていました。
📝まとめ:光と影をどう見るか
保冷バッグ販売は、一見すると「新しい働き方スタイル」や「フードロス削減への貢献」といった光の側面を持っています。しかしその裏には、元締めによる利益独占、販売員への負担、法律的なグレーゾーン、そして消費者が抱えるリスクという影の部分が色濃く存在します。
街角で見かけるあの光景は、私たちの社会が抱える“食品ロス”や“働き方の多様化”という課題を象徴するものでもあります。けれど同時に、“労働搾取”や“規制の穴”といった問題も浮き彫りにしているのです。
こうして見てみると、暮れなずむ街の光と影の中でキャリーバッグを引く彼女たちも、業界の内包した光と影をまといながら頑張っているということがわかりますね(;´・ω・)
私は次に彼女たちに遭遇した時は、目を背けるのではなくて、目をかけようと思いました💦
長々と、お目汚し失礼いたしました。<m(__)m>w