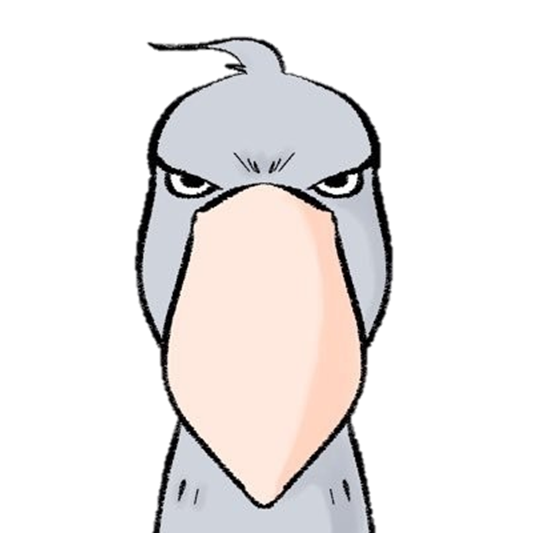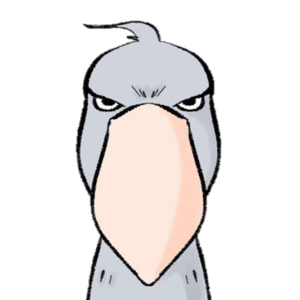18世紀末のヨーロッパ音楽史を語るうえで、モーツァルトとベートーヴェンの関係ほど多くのロマンが付与されてきたものはありません。「ウィーンで二人が出会い、モーツァルトが若きベートーヴェンの才能を見抜いた」という逸話は、多くの書籍や映像作品で描かれ、天才の系譜として語り継がれています。しかし、こうした物語には史料上の注意が必要です。ここでは、二人の接点にまつわる事実と仮説を整理し、神話に隠れた現実を見ていきましょう。
1. “出会い”の史実とその信憑性
ベートーヴェンが初めてウィーンを訪れたのは1787年、16歳のときとされています。このとき、モーツァルトは既にウィーンで活躍しており、31歳の円熟期にありました。多くの伝記が「この時、ベートーヴェンはモーツァルトの元を訪れ、その才能を披露した」と記しますが、これを裏付ける一次資料は存在しません。
よく引用されるエピソードとして、「即興演奏を聴いたモーツァルトが“この少年に注意を払え。いつか世界に語らせるだろう”と言った」というものがあります。しかし、この逸話は19世紀半ば以降に広まったもので、モーツァルトの同時代の書簡や記録には記されていません。音楽史研究者たちは、後世の美化やベートーヴェン崇拝の風潮が生んだ“伝説”の可能性が高いと指摘しています。
では、二人が本当に会っていなかったのかと言えば、完全な否定もできません。ウィーン滞在中のベートーヴェンが、ピアノの師を求めてモーツァルトに紹介状を書かせようとした形跡がある、という記録もあります。ただし、母の病気で急遽ボンに帰郷したため、深い師弟関係が築かれるには至りませんでした。
2. 音楽的影響と初期作品
直接的な師弟関係がなかったとしても、ベートーヴェンがモーツァルトの音楽に強い影響を受けたことは疑いありません。交響曲第1番(1800)には、モーツァルトの「交響曲第40番」や「ジュピター交響曲」を思わせる古典的均整と和声の運びが見られます。また、ピアノ協奏曲第1番・第2番には、モーツァルトの協奏曲に通じる構成美と対話的なソロの扱いがあります。
興味深いのは、ベートーヴェンがモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」序曲を熱心に研究していたという記録です。ベートーヴェンのスケッチ帳には、このオペラの主題を書き写した跡があり、後の交響曲第3番「英雄」や第5番「運命」に通じる動機処理の萌芽が感じられます。モーツァルトの影響を“模倣”から“発展”へと変えていったのです。
3. モーツァルトの死後に芽生えた“超えるべき存在”
モーツァルトが1791年に死去したとき、ベートーヴェンは21歳。直接の交流はほとんどなかったものの、その死は若き作曲家に大きな衝撃を与えました。ベートーヴェンはハイドンに師事しつつも、常にモーツァルトの作品を学び、「彼を超えること」を目標にしたと伝えられています。
例えば、弦楽四重奏曲作品18(1801)には、モーツァルトの晩年の四重奏曲への明確なオマージュが感じられます。しかし同時に、強烈な動機展開や力強い終止法といった“ベートーヴェンらしさ”が前面に出ており、「影響を受けつつ、既に別の地平を歩み始めている」ことがわかります。こうしてベートーヴェンは、モーツァルトの美を継承しながら、自らの革新性で古典派の枠組みを広げていきました。
4. 神話と事実の間で
二人の関係を語るとき、私たちはしばしば「天才が次の天才を認めた」という美しい物語に魅了されます。しかし、史実として確実に言えるのは、「モーツァルトの音楽がベートーヴェンの形成期に不可欠な存在だった」ということです。直接的な師弟関係があったかどうかよりも、その音楽的遺産がどう引き継がれ、変容し、次代の表現を切り拓いたかに注目すべきでしょう。
注意すべきは、後世の伝説に流されて史実を誤解しないこと。クラシック音楽史は、天才たちの人間的な営みの積み重ねであり、そこにリアルな葛藤と試行錯誤が存在します。モーツァルトとベートーヴェンの“関係”もまた、神話ではなく音楽そのものの中に息づいているのです。
このように、史料の不足や後世の脚色を踏まえて「事実」と「影響」を整理することで、モーツァルトとベートーヴェンの関係は、単なるロマンではなく音楽史のダイナミックな連続性として見えてきます。