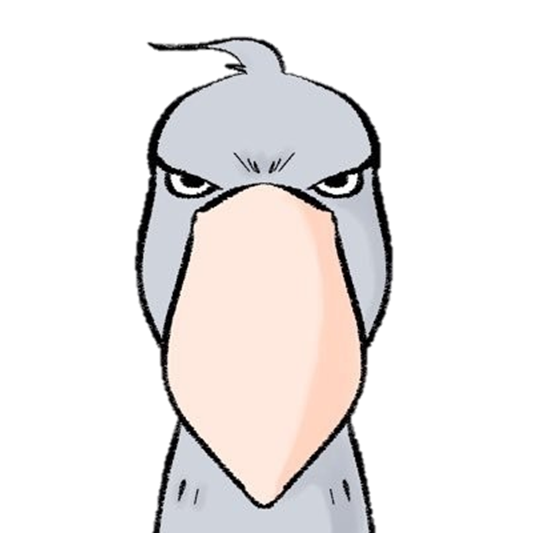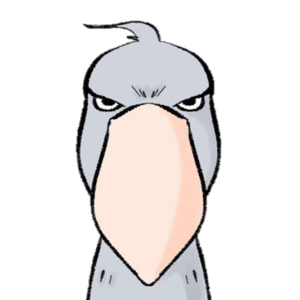8月18日は「高校野球記念日」――甲子園のはじまりをたどって
夏といえば、真っ青な空に響き渡る金管楽器の応援、砂ぼこり舞うグラウンド、そして球児たちの汗と涙。日本の夏の風物詩といえば「夏の甲子園」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。そんな甲子園の原点が生まれた日が、1915年(大正4年)8月18日。この日を記念して「高校野球記念日」と呼ばれるようになりました。
はじめての全国大会は、たった10校から
今では全国4000校以上が参加する高校野球ですが、最初の大会はとても小さなものでした。大阪府の豊中球場に集まったのは、北海道から九州までのわずか10校。観客席も、今の甲子園のスタンドのような大規模なものではなく、こじんまりとしたものでした。
けれども、試合が始まればそこは本気のぶつかり合い。真っ白なボールを追いかける球児の姿は、当時の人々の胸を打ちました。優勝を手にしたのは「京都二中(現在の京都府立鳥羽高校)」。これが記念すべき第1回のチャンピオンです。
ちなみに当時は、今のようにしっかりしたルールが整っていたわけではありません。ボールの硬さや縫い目が試合ごとに違ったり、延長戦が長引いて日が暮れ、結局「今日はここまで、また明日」なんてこともあったそうです。ちょっとユルさを感じるエピソードですが、そこにまた“草創期らしさ”が漂っています。
豊中から鳴尾、そして甲子園へ
初めての大会が成功すると、翌年からは兵庫県の鳴尾球場で開催されました。しかし試合を見たい観客はどんどん増えていき、鳴尾球場でも手狭になっていきます。
そこで1924年に誕生したのが、今も「高校野球の聖地」と呼ばれる甲子園球場です。実はこの球場、高校野球のために作られたわけではなく、阪神電鉄が沿線の開発を盛り上げるために建設したもの。それが結果的に、高校野球の大舞台として定着したのだから面白いですね。
「甲子園」という名前の由来も少しユニークです。完成した1924年が、干支の“甲子(きのえね)”の年だったことから名づけられました。偶然のようでいて、今では「甲子園」という言葉自体が“高校野球そのもの”を表すようになっているのだから、不思議な縁を感じます。
戦争による中止、そして復活
高校野球にも、暗い時代がありました。1941年、戦争が激しくなると「ぜいたくなスポーツは控えるべき」として大会は中止に。ユニフォームを着てグラウンドを駆け回るはずの若者たちが、銃を持って戦場へと送り出されることになったのです。
戦後、焼け野原の日本に再び高校野球が戻ってきたとき、その光景は人々に大きな勇気を与えました。壊れてしまった街に響く金属バットの音、白球を追う真剣なまなざし。それは「日本はきっと立ち上がれる」と多くの人に思わせる、希望の象徴でした。
甲子園の小ネタあれこれ
ここで、ちょっとした裏話をいくつかご紹介します。
- 甲子園の黒土
試合が終わると、球児たちがグラウンドの土を袋に詰めて持ち帰る姿を見たことがあるかもしれません。あの土は「甲子園の黒土」と呼ばれます。実はただの自然の土ではなく、グラウンドが雨でぬかるまないように工夫して混ぜ合わせた“特製の土”なんです。毎年補充されるので、実際には何層もの“歴史のミルフィーユ”のようになっています。 - アルプススタンドの応援
高校野球といえば応援も大きな見どころ。実はアルプススタンドという名前は、甲子園球場ができた当初に「山の斜面のように高くそびえて見える」ことからつけられたニックネームです。球児たちを見守るスタンドには、そんな遊び心が込められていたんですね。 - 地方大会の熱さ
「甲子園に出る」こと自体が夢なので、地方大会も毎年ものすごい盛り上がりを見せます。実は甲子園よりも地方大会のほうが観客数が多い試合があるくらい。地元の人にとっては“この一戦こそが本番”なのです。
夏の甲子園が持つ意味
第一回大会はわずか10校、観客も数千人規模。それが今では全国の高校球児の憧れとなり、テレビやネットを通して何百万人もの人が見守る大会になりました。勝敗だけでなく、そこに生まれるドラマ――大逆転、惜しいエラー、泣き笑いする球児の姿――が、見る人の心を揺さぶります。
だからこそ、8月18日の「高校野球記念日」は、単なる“歴史の一日”ではなく、日本の青春と情熱が始まった日ともいえるのです。
今年もまた、甲子園では新しい物語が生まれます。グラウンドに立つのは同じ高校生。でも、その一瞬一瞬は二度と帰ってきません。100年以上前、豊中球場で白球を追った球児たちと同じように、今も未来の誰かが「忘れられない夏」を刻んでいるのです。