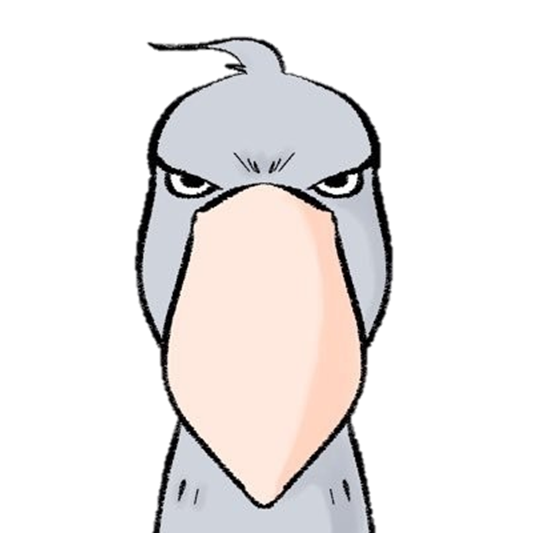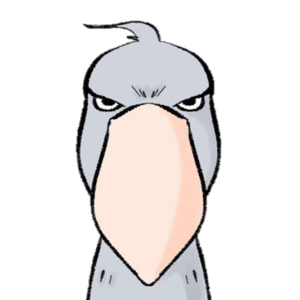8月19日は「俳句の日」――五七五に込められた小さな宇宙
8月19日は「俳句の日」。読み方を工夫して「は(8)・い(1)・く(9)」という語呂合わせからつけられた記念日です。たった17音の短い言葉の中に、季節の移ろいや人の心を込める――日本独自の文化「俳句」を改めて楽しもうという日です。
世界一短い文学
俳句は、世界で一番短い詩ともいわれます。基本は五・七・五の17音だけ。ちょっとしたつぶやきのような短さなのに、不思議と広い景色や心の動きを感じさせてくれます。
例えば松尾芭蕉の有名な句、
「古池や 蛙飛び込む 水の音」。
わずか17音ですが、目の前にひろがる静かな池の風景、そして水音が響く瞬間の鮮やかさが、ぱっと心に浮かびます。まさに「短い言葉で無限を描く」文学ですね。
記念日を作ったのは俳人たち
この「俳句の日」を呼びかけたのは、現代の俳人や俳句愛好家の団体でした。学校教育の中でも俳句は親しまれてきましたが、改めて“子どもから大人まで、気軽に俳句を楽しんでほしい”という願いが込められています。
実際、この日には全国各地で「俳句甲子園」や俳句のイベントが開かれることがあります。俳句甲子園は高校生の大会で、ただ俳句を詠むだけでなく、お互いの句を鑑賞して議論するのが特徴。青春の一コマとして、なかなか熱い戦いが繰り広げられます。
ちょっとした小ネタ集
- 芭蕉の旅好き
「奥の細道」で有名な松尾芭蕉は、生涯のほとんどを旅に費やしました。今でいえばリュックひとつ背負って国内をぐるぐる回るバックパッカーのような存在。しかも宿代や食費は、弟子や土地の人々の支援でまかなっていたそうです。いわば“クラウドファンディング俳人”だったのかもしれません。 - 正岡子規と野球
俳句を近代文学へと進化させた正岡子規。実は大の野球好きで、日本に「ベースボール」を「野球」と訳したのも彼だといわれています。つまり、夏の甲子園と俳句には、意外なところでつながりがあるんですね。 - 季語の奥深さ
俳句には「季語」が欠かせません。これは単なる季節の言葉ではなく、その背後にある情緒や文化までも呼び起こします。たとえば「桜」といえば春の花ですが、日本人ならそこに「別れや旅立ち」「はかない命」といったイメージまで感じます。17音の中に広い世界を呼び込めるのは、季語の力のおかげなのです。
現代風の俳句
今の時代、俳句はかしこまったものだけではありません。SNSでは「#俳句チャレンジ」として日常を五七五で表現する遊びが広がったり、芸人さんやタレントが俳句に挑戦するテレビ番組も人気です。
たとえば、
「Wi-Fiが 弱くて進まぬ 夏の宿」
なんて句も立派な俳句。季語に「夏」を入れておけば、ちょっと笑える“現代の生活句”になります。こうした柔らかい楽しみ方ができるのも、俳句の懐の深さです。
読む人によって変わる世界
俳句の面白さは、読む人の想像で景色が変わるところにもあります。たとえば「夕立や 母の呼ぶ声 濡れて聞く」という句があったとします。これを読んだ人の中には、自分の子どものころの思い出を重ねる人もいれば、どこか懐かしい田舎の風景を思い浮かべる人もいるでしょう。
たった17音の言葉が、読む人の数だけ違う物語を生み出す。これは小説や映画とはまた違う、俳句ならではの魅力です。
俳句の日にできること
8月19日は、そんな俳句を身近に感じてみるチャンスの日です。肩ひじ張らなくても大丈夫。ベランダから見える空や、昼ごはんに食べたそうめん、セミの声でもいいのです。気になった景色を五七五にしてみるだけで、普段とは違う視点で日常が見えてきます。
たとえば、
「かき氷 頭にキーンと 夏まぶし」
「蝉の声 テレビの野球 消えにけり」
なんて句をひねってみると、自分の中の“夏”がちょっと特別に思えてきます。
俳句は続いていく
千年以上前の和歌から始まり、江戸の芭蕉、明治の子規、そして現代の私たちまで――俳句はずっと人の心をつなぎ続けています。短いけれど、そこにこめられる感情は果てしなく広い。
8月19日の「俳句の日」は、そんな小さな宇宙にふれてみるきっかけの日。きっと今日もどこかで、新しい五七五が生まれているはずです。