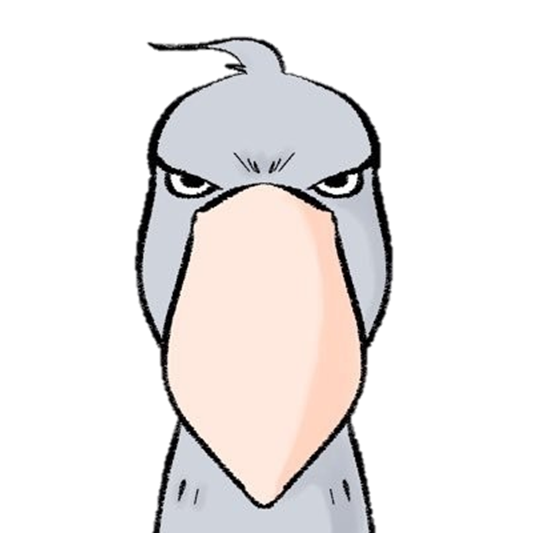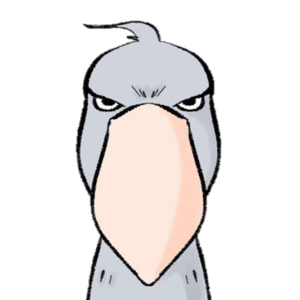国民栄誉賞?とても大仰な名前の賞を考える
皆さんこんぬつは!!けだま。です(・ω・)ノ
その昔嶋大輔さんは、猛々しくも『男の勲章』なんて歌い上げたものですが、人間誰しも勲章、もしくは栄誉を讃えられる事を欲するもの……様々な勲章が溢れる現代社会において最高峰に位置するのが、国民栄誉賞あることは衆目の一致するところでしょうね~
しかしなぜ「国民栄誉賞」は人々を惹きつけるのか?今日は『最高の勲章』国民栄誉賞の成り立ちと歴史を深掘りして参りましょう~!!(≧▽≦)
9月5日は「国民栄誉賞の日」とされています。1977年のこの日、プロ野球のスーパースター・王貞治さんが初めてこの栄誉を受けたことにちなむ記念日です。
国民栄誉賞とは「国民に広く敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績を挙げた人々」に贈られるもの。首相が判断して授与するため、スポーツや芸術など分野を超えて様々な人物が受賞してきました。
勲章や文化勲章のように制度的に位置づけられたものではなく、首相の裁量が大きいことから、その存在意義や選定基準は常に議論の的となります。けれども、多くの人にとって「国民栄誉賞」と聞けば、「日本中が感動したあの瞬間」を思い出させてくれる、不思議な響きをもった賞なのです。
続いて、歴代受賞者をざっくり覗いてみましょう!!
第1号:王貞治 ― ホームラン世界記録の男
国民栄誉賞の第1号は、読売ジャイアンツの王貞治さん。1977年9月、通算756号ホームランを放ち、ベーブ・ルースを超える世界記録を樹立しました。
「一本足打法」に象徴される独自のスタイル。努力と研究を重ね、自らを鍛え抜き続けた王さんの姿は、戦後の日本人に「勤勉さと夢の両立」を示しました。
当時、野球は国民的スポーツであり、王さんの一打は連日ニュースのトップを飾りました。子どもたちがバットを振りながら「王選手みたいになりたい」と憧れを抱いたことは言うまでもありません。
王さんが初代受賞者に選ばれたのは必然でした。国民に夢と勇気を与えた功績に加え、清廉で真摯な人柄が「日本人が誇れる象徴」とされたのです。
第2号:古賀政男 ― 昭和歌謡の父
1978年に受賞したのは作曲家・古賀政男さん。「影を慕いて」「丘を越えて」など、数多くの名曲を世に送り出し、戦前から戦後にかけての日本人の心に寄り添い続けました。
古賀メロディーは、どこか郷愁を誘う旋律で、多くの人に「自分の人生の一部」のように親しまれました。戦後の混乱期、復興のただ中、喜びも悲しみもその歌とともにあったと言っても過言ではありません。
文化人として初の国民栄誉賞受賞者となった古賀さんは、「この賞は国民の皆さまにいただいたもの」と語りました。音楽が国境や世代を超えて人々の心を結ぶ力を持つことを示した存在でもありました。
第3号:長谷川町子 ― サザエさんと国民の生活
1985年、漫画家の長谷川町子さんが受賞します。作品『サザエさん』は戦後の日本社会を映す鏡であり、磯野家の日常は庶民の生活と深く重なり合いました。
テレビアニメ版の放送が始まったのは1969年。以来、日本の「日曜日の夕方」はサザエさん一家とともにありました。登場人物たちの何気ない会話やハプニングが「どの家庭にもある風景」として共感を呼び、世代を超えて親しまれています。
長谷川さんは寡黙で公の場にあまり出なかったため、受賞当時は驚きの声も上がりました。しかし、国民生活に寄り添い続けた功績を考えれば、まさに「国民栄誉賞にふさわしい漫画家」だったと言えるでしょう。
第4号:衣笠祥雄 ― 鉄人の精神
1987年に選ばれたのは、広島東洋カープの衣笠祥雄さん。プロ野球で2215試合連続出場という「鉄人」記録を打ち立てました。
ケガをしても休まない姿勢は、ファンに深い感動を与えました。特に、鎖骨を骨折しながらも翌日代打で出場した逸話は有名です。「チームのために」という思いを貫いたその姿は、勝利よりも大切な「誇り」を感じさせました。
衣笠さんの国民栄誉賞は、努力と忍耐の価値を社会に強く印象づけました。スポーツが単なる勝ち負けではなく、人の生き方そのものを照らすものだと示したのです。
第5号:美空ひばり ― 昭和が生んだ歌姫
1989年に、戦後歌謡を代表する歌手・美空ひばりさんが受賞しました。前年に亡くなったことを受けての「追贈」でした。
「リンゴ追分」「川の流れのように」など数々のヒット曲は、日本人の心を映す歌として語り継がれています。特に晩年に歌った「川の流れのように」は、国民栄誉賞授与のきっかけとなったとも言われます。
戦中の子どもスターから始まり、激動の昭和を駆け抜けたひばりさん。時にスキャンダルや病気に苦しみながらも、歌で人々を励まし続けました。その生涯が「国民に愛され、希望を与えた」と評価されたのです。
第6号:千代の富士 貢 ― 小さな大横綱
1989年、同じ年に横綱・千代の富士も受賞しました。小柄ながら筋骨隆々とした体で「ウルフ」の異名を取り、相撲界を席巻しました。
53連勝を記録し、優勝31回は当時の史上最多。相撲人気を再び高めた立役者でもあります。
体格的に不利とされた中で、鍛錬と工夫によって勝ち続けた姿は、挑戦の象徴でした。千代の富士は引退会見で「体力の限界」と語り、潔さもまた人々の心に残りました。
第7号:藤山一郎 ― 清らかな歌声と国民的歌手
1992年、国民栄誉賞に選ばれたのは、歌手・藤山一郎さんでした。「長崎の鐘」「青い山脈」などを歌い上げたその声は、日本人の暮らしとともにありました。
藤山さんの歌声は澄み切ったテノールで、戦前から戦後にかけて、苦しみや希望の時代を支える響きとなりました。ラジオやレコードを通じ、国民が一緒に口ずさむ歌の数々は、やがて「昭和の記憶」とも呼べる存在となったのです。
彼は音楽を単なる娯楽ではなく、「人々の心を結ぶ文化」として体現しました。晩年まで衰えぬ声量を保ち続けた藤山さんの姿は、「誠実に芸を磨くことの尊さ」を示しました。
第8号:長谷川町子 ― サザエさんと国民の生活
1992年には、すでにご紹介した漫画家・長谷川町子さんも受賞しました。国民的アニメ『サザエさん』を生み出した功績は、世代を超えた共感を集め、「日本の家庭像」を象徴するものとなりました。
磯野家の暮らしはいつの時代も人々の心に寄り添い、「身近な幸せ」を思い出させてくれる存在でした。
第9号:服部良一 ― 昭和歌謡を彩った作曲家
1993年に受賞したのは作曲家・服部良一さん。代表曲「青い山脈」「東京ブギウギ」など、戦後日本を明るく元気づける音楽を数多く生み出しました。
彼の作品はジャズやポップスの要素を取り入れ、新しい時代の息吹を感じさせるものでした。敗戦から立ち上がる日本に必要だった「前を向く力」を、音楽で表現し続けたのです。
第10号:渥美清 ― 寅さんと日本人の心
1996年、俳優・渥美清さんが国民栄誉賞を受賞しました。『男はつらいよ』シリーズで演じたフーテンの寅さんは、日本人にとって「隣にいてほしい人」の象徴でした。
旅先で出会い、恋に破れ、しかし人情を忘れない寅さん。渥美さんが生涯をかけて演じ続けたその姿は、時代を超えて「日本人の優しさ」を映し出しました。
渥美さんは人前に出ることを好まず、私生活を謎めかせた存在でしたが、スクリーンでの彼の笑顔は、国民にとって心の支えであり続けました。
第11号:吉田正 ― 戦後歌謡のもう一人の巨匠
1998年には作曲家・吉田正さんが受賞。「いつでも夢を」「有楽町で逢いましょう」など、昭和歌謡の黄金期を築きました。
彼のメロディーは都会の華やかさと庶民の哀愁を絶妙に織り交ぜ、日本人の心情を巧みに表現しました。音楽を通じて「夢と現実のはざま」を描き続けた存在でした。
第12号:森繁久彌 ― 国民的俳優として
2009年には俳優・森繁久彌さんが受賞。舞台、映画、テレビに幅広く出演し、戦後の日本演劇を支えました。温かみのある演技とユーモアで、世代を超えて愛された俳優です。
長いキャリアの中で積み重ねられた役柄の数々は、日本人の人生そのものを映し出す鏡のようでした。森繁さんの受賞は、「大衆文化の力」を改めて示すものでした。
第13号:なでしこジャパン ― 世界一に輝いたサッカー女子代表
2011年、FIFA女子ワールドカップで初優勝を成し遂げた日本女子サッカー代表「なでしこジャパン」が団体として国民栄誉賞を受賞しました。
東日本大震災から間もない時期に掴んだ世界一の栄冠は、日本中に勇気と希望をもたらしました。澤穂希選手が大会MVPと得点王を同時受賞し、「小柄でも世界に通じる」日本サッカーの可能性を示した瞬間でした。
団体としての国民栄誉賞は初めてであり、スポーツの力が人々の心を支える証明となりました。
第14号:吉田沙保里 ― 女子レスリングの絶対女王
2012年、女子レスリングの吉田沙保里選手が受賞しました。世界大会で13連覇、オリンピック3連覇という前人未到の偉業を成し遂げ、「霊長類最強女子」と呼ばれるほどの圧倒的強さを誇りました。
吉田選手の魅力は強さだけでなく、勝利後に見せる笑顔や涙にありました。国民に「努力と情熱が世界を変える」ことを教え、スポーツを通して多くの女性や子どもたちに夢を与えました。
第15号:伊調馨 ― オリンピック4連覇の快挙
2016年には、女子レスリングの伊調馨選手が受賞。アテネからリオまで、オリンピック4大会連続で金メダルを獲得するという歴史的偉業を成し遂げました。
その姿勢は華やかさよりも「静かな強さ」。淡々と鍛錬を重ね、試合で圧倒的な力を見せる彼女の生き方は、努力の結晶そのものでした。吉田沙保里選手と並び、日本女子レスリングの黄金時代を築いた立役者でした。
第16号:羽生善治 ― 永世七冠の棋士
2018年には、将棋棋士・羽生善治さんが受賞しました。史上初の「永世七冠」を達成し、30年以上にわたり第一線で活躍を続けたその功績は、盤上の芸術と呼ぶにふさわしいものでした。
羽生さんの勝負姿勢は、ただ勝つためだけでなく、将棋の可能性を広げるものでした。時に敗北をも糧とし、常に新しい研究を重ねる姿は、知の探求者そのもの。国民栄誉賞の受賞は、知的競技が社会に与える影響の大きさを物語りました。
第17号:井山裕太 ― 前人未到の囲碁七冠制覇
同じ2018年、囲碁棋士・井山裕太さんも受賞しました。囲碁界で史上初となる七大タイトル同時制覇を達成し、長らく停滞気味だった囲碁界に新たな光をもたらしました。
幼いころから「天才少年」と呼ばれた井山さんは、国内外で活躍し続け、囲碁の魅力を広める役割も担いました。将棋と並び、伝統文化としての知的スポーツの存在感を国民に再認識させたのです。
第18号:大谷翔平 ― 二刀流で世界を驚かせる
2021年、MLBエンゼルスで投打の二刀流として大活躍した大谷翔平選手が国民栄誉賞の打診を受けました。しかし本人は「まだ道半ば」として丁重に辞退しました。
正式な受賞には至らなかったものの、このエピソード自体が大谷選手の人柄とストイックさを表す象徴となっています。いずれ国民栄誉賞に選ばれるであろう「未来の受賞者」として、すでに国民の心に刻まれています。
第19号:羽生結弦 ― 氷上のレジェンド
2022年、フィギュアスケートの羽生結弦さんが受賞しました。ソチ、平昌とオリンピックを連覇し、東日本大震災を乗り越えて挑戦し続けた姿は、多くの人に希望を与えました。
彼の演技は技術だけでなく芸術性にも優れ、「4回転半ジャンプ」に挑み続ける姿勢は挑戦者そのもの。競技を超えて「人としてどう生きるか」を示した存在でした。
羽生さんの受賞は、スポーツがもたらす感動の究極形とも言えるものでした。
― 国民栄誉賞が映す日本人の心と未来への課題
ハアハア(*´Д`)手が疲れました。苦笑
こうして振り返ってみると、国民栄誉賞の歴史は、そのまま戦後から現代に至る日本社会の歩みを映す鏡のように見えてきます。野球の王貞治さんが初代受賞者として「夢を叶える努力の象徴」となり、古賀政男さんや美空ひばりさんといった歌の巨星たちが「人々の心を支える文化の力」を示しました。相撲界の千代の富士やレスリングの吉田沙保里選手は「強さと挑戦」の価値を、渥美清さんや長谷川町子さんは「人情や家族の温かさ」を、羽生善治さんや井山裕太さんは「知と探求心の大切さ」を、それぞれ私たちに伝えてくれました。
つまり国民栄誉賞は、単なる表彰ではなく、**「いま日本人がどんなものを誇りに思い、どんな希望を抱きたいか」**を映し出すものなのです。
しかし一方で、この賞には常に課題も指摘されてきました。第一に「選考基準があいまいであること」。スポーツ選手や芸能人に偏りがちで、科学者や教育者など社会を根底から支える人々の受賞は少ないのが現実です。第二に「授与のタイミングが政治的に利用されているのではないか」という疑念。首相の判断で決まるため、時の政権の人気取りや世論操作に結びつけられる危うさを抱えています。そして第三に「本人が辞退するケースもある」という点。大谷翔平選手のように「まだ道半ば」として辞退した例は、その謙虚さを示す一方で、国民栄誉賞そのものの位置づけの難しさを浮き彫りにしました。
それでもなお、この賞が多くの人々を惹きつけてやまないのはなぜでしょうか。それは国民栄誉賞が「誰もが共有できる感動の記憶」を形にする役割を持っているからです。王選手の一打、なでしこジャパンのゴール、羽生結弦さんの氷上での舞…。その瞬間を思い出すと、私たちは「自分もあの時、胸を熱くした」という記憶を取り戻すことができます。賞そのものよりも、むしろ「感動を国全体で共有する喜び」こそが、人々を惹きつけているのです。
これからの国民栄誉賞は、単に「過去の偉業」をたたえるだけでなく、「未来にどんな希望を残すか」という観点がますます大切になるでしょう。科学や教育、地域社会での活動など、光が当たりにくい分野にも広げることで、日本人の価値観をより豊かに映すことができるはずです。
国民栄誉賞の日である9月5日。私たちは、歴代受賞者たちの偉業を称えるだけでなく、自分自身に問いかけてもよいのかもしれません。「私にとって誇りとは何か」「次の世代に伝えたい希望とは何か」。そう考えると、この賞は単なるメダルや称号ではなく、**国民一人ひとりの心に宿る“物語”**なのだと気づかされます。
国民栄誉賞は、まだ完成していない物語です。これから誰が受賞し、どんな瞬間が日本中を熱くするのか。そのたびに、私たちは再び一緒に涙し、拍手を送り、未来への希望を見出すことでしょう。
歴代受賞者のどの方々も世の中の常識にとらわれず、『ツッパリ』続けた結果の栄誉なのかもしれませんね( *´艸`)
。