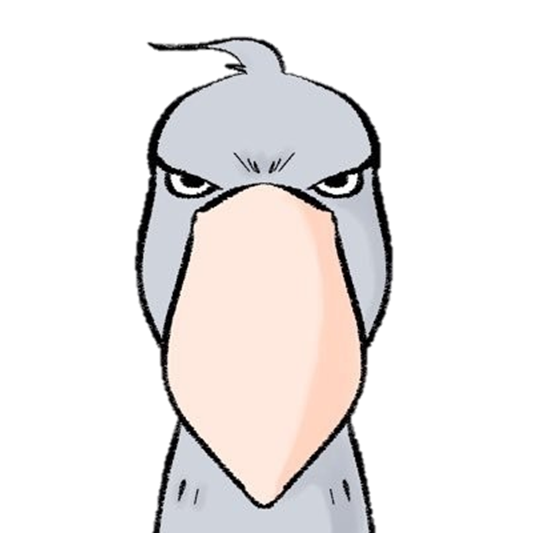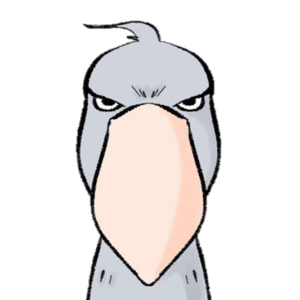献血記念日(8月21日)とは?日本における献血の歴史と意外なエピソード
8月21日は「献血記念日」
毎年8月21日は「献血記念日」。1964年(昭和39年)のこの日、日本で初めて「売血」から「献血」へと大きな転換がなされました。
厚生省(現・厚生労働省)が、売血制度を廃止し、輸血に必要な血液を「善意の献血」によって集める方針を決定したのです。
当時の日本は高度経済成長期。工場が立ち並び、新幹線も走り始め、東京オリンピックを控えた活気ある時代でした。しかし、医療の現場では深刻な課題がありました。それが「血液の安全性」です。
売血の時代とその問題点
戦後の日本では血液を得る方法として「売血」が一般的でした。血を売ることで生活費を得る人も多く、貧困層にとっては重要な収入源。しかしここには大きな落とし穴がありました。
売血を繰り返すことで体調を崩す人が続出。さらに生活苦から健康状態が悪いまま提供される血液も少なくなく、輸血によって肝炎などの感染症が広がるリスクが非常に高かったのです。医療の現場からは「安全で安定的な血液供給の仕組みが必要だ」という声が高まりました。
「献血」への転換
こうした背景のもと、1964年8月21日に厚生省が発表したのが「売血制度の廃止と献血制度への移行」。以後、日本は「善意の提供」に基づく献血を基本とする国となりました。
この決定は、単なる医療制度改革にとどまらず、「人と人とが互いを支え合う社会」への転換を象徴する出来事でもありました。
初期の献血キャンペーンとその工夫
当時はまだ「血をタダであげるなんて…」という意識も根強かったため、普及には工夫が必要でした。そこで登場したのが「献血車」。街角や駅前に停められ、気軽に立ち寄って献血できる仕組みを広げました。
また、献血者に記念品を配ったり、学校や企業で集団献血を呼びかけたりするなど、全国規模でのキャンペーンが展開されていきます。こうして少しずつ「献血=社会貢献」という意識が浸透していきました。
赤十字の役割
献血制度を支えてきたのが「日本赤十字社」。献血ルームの整備や献血バスの運営を通じ、安定した血液供給を実現するために大きな役割を担ってきました。
特に大災害や事故の際には、必要な血液を迅速に確保するためのネットワークが力を発揮しています。
世界の献血事情
ちなみに世界では献血の仕組みは国によって大きく異なります。アメリカでは報酬付きの献血(正確には「血漿提供」)が今も残っていますし、中国や一部の国々では献血の習慣がまだ十分に根付いていません。
その中で日本は「100%自発的な献血」で医療を支えている、世界的にも珍しい国のひとつです。
若者の献血離れ?
ここ数年、少子高齢化の影響で若者の献血者数が減っていることが課題となっています。日本赤十字社によると、医療現場で必要とされる血液の約8割は50歳以上の患者さんに使われています。しかし献血できるのは16〜69歳までの健康な人。今後、若い世代の参加がますます重要になっていきます。
コーヒーと献血の関係?ちょっとした小ネタ
実は献血ルームに行くと、無料でジュースやコーヒーが飲めたり、お菓子がもらえたりすることをご存じでしょうか。これは「血を抜いたあとに血糖値や水分量を保ち、体調を崩さないため」という医学的な配慮なのですが、同時に「ちょっとしたご褒美感」を演出する役割もあります。
一部の常連献血者の間では「今日はどんなお菓子があるかな?」と密かな楽しみにしている人もいるのだとか。
献血は「未来への贈り物」
輸血用の血液には保存期限があります。赤血球は約21日、血小板はたった4日しかもちません。つまり、誰かが献血をしてくれて初めて、明日必要な患者さんに届くのです。
8月21日の「献血記念日」は、医療の歴史を振り返ると同時に、「自分の血液が誰かの命を救うかもしれない」という大切な事実を思い出させてくれる日でもあります。
まとめ
- 8月21日は「献血記念日」
- 売血から献血への大転換が行われた日
- 赤十字や献血車が普及に大きく貢献
- 現代は若者の献血参加が課題
- 献血は「未来の誰か」へのプレゼント